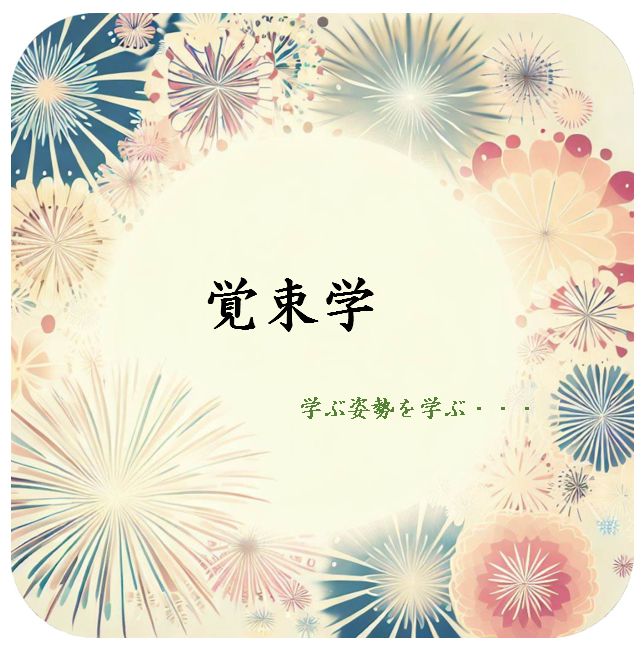
其仙流 玄流敬典 覚束学
「覚束学とは」
「覚束学」とは「覚束(おぼつか)ない者」を教え導く学問という意味合いです。
「指南業」「占い業」とはそう単純な仕事でもなく、又簡単に理解も出来る様な稚拙な学問でもありません、又「占い」は昔から「運勢学」という「学問」でもあります、精神性や神秘性を帯びた側面はありますが、だからと言って「神秘思想、オカルト霊感」の類でもありません。
古書「麻衣神相法」に「之妄りに教えるべからず」と記されており、余程の覚悟を以ってしても、又余程の才覚ある者でも正しく理解が出来るものではない故に、妄りに後世に教え伝えると曲がり、歪んで伝わってしまう、と先人達の憂いの念が近代になるに連れ顕著に現れています。
今や「占いの概念」に「万人が共有する一定の定義」が出来ておらず、各占い師の言ったもん勝ちの側面が非常に強く、その概念に共感できる人が多いか少ないかで「本物かどうかの認識をしている」状況が昨今の占い業界です。
又、テレビ、雑誌、ネットなどのメディアも「本物か偽物か」「一流人か二流以下か」で「占い師」を選ばずに「数字が取れるか取れないか」「売れるか売れないか」で判断しているので状況は更に混沌としています。
平和ボケも手伝って、この様な状況下の元に多く人が「本物とは」「占いとは」「占い師とは」という根本が分かっていないという状態なのです。
其仙流は「本物」を教える流派です、「本物に成る為の占い教室」です、その為には皆さんの「不純物」を先ずは取り除く事から始めなければいけません。
その代表例は「間違った占法」を知る事です。
殆どの門下生は「自分が信じている占法」はきっと「本物だ」と思っているでしょうが、例えば「タロット占い、九星気学、姓名判断、マヤ暦占い、世間一般的な相学、スピリチュアル、オラクルカード、算命学、四柱推命」などなどは全て原理が間違っているか、原理も無い全くの思い込みの占法です。
占いの占法は必ず「運勢を何故見る事ができるのか」、という「原理、原則」が存在します、中には占いは精神力を使用するものだから「原理、原則」などは存在しません、と主張する人もいますが、その様な主張をする人は「占い」を本質的に理解出来ていない人の愚かな主張です。
確かに「占い」には「精神力」を使う側面もありますが、それでも一定の原則が存在します、例えば「剣道、茶道、華道、弓道」など他にもありますが、これらは「技術と精神性」との両立を元に一つの到達点、つまり「奥伝、真骨頂、真理」へと達する事を一つの目的とします、つまり「精神性」を「漠然、曖昧」としたものと扱わずに具体的に精神性の中にそれぞれの真理を見出す事を求めるものです。
茶道の茶室は「小宇宙」に見立て、その茶碗の中に宇宙を悟る事が出来るかどうかを求める事も茶道の一つの到達点です、弓道も的の一点を射抜く為の集中力を得る為に一点を想像します、その一点を射る精神と体、そして技術が絶妙な塩梅で統一されて初めて的の一点を射抜く事が出来ます。
この様に「精神性」と言っても一定の理屈が存在するのです、曖昧で漠然としやすい「精神性」ですが、その中にもしっかりとした理屈に基いた流れを見出す事が望まれます。
違う例えをすれば、例えば「神社やお寺」で願い事をする時に「強く念じた」所で願いが叶いますか?
第一義「三徳、素直」 「素直」無くして本物には成れない
其仙流の修行や学問を学ぶ時には様々な「精神」がありますが、その中でも至る所に出て来る「精神」があります、それは「三徳」です、「三徳」とは「素直、謙虚、感謝」の三つの事で、その中でも最も重要な精神が「素直の養い」です。
「素直無くして真実は分からない」「素直無くして本質は悟れない」「素直無くして道理は得られない」と代々口伝で伝わっています。
「学びにも素直の姿勢」「指南の現場でも素直の構え」「運勢を判ずる時にも素直に観る」・・・兎角「本物の指南者は素直の養い」を最も尊び、其仙流でも生涯を通して「素直さ」を養い、又、先生や師匠、師範などからその養いの度合いを観られ判断されます。
この「素直さ」を「そんな事を今更」とか「素直の養いなんか特別必要無い」とか「素直さは自分はしっかりと心得ている」と思っている人は、この先中々に苦労をするでしょう、多くの人々が「素直さ」を「十分養っている」「素直さよりも優先するべき事がある」などと思い込んでいますが、それは幻想に過ぎません、多くの人々が「素直さの養い」が不十分な状態です。
「素直さ一つ」深く養っただけでも運は根深く付きます、又幼い頃から素直の養いをしていると、透明感を以って物事を判断でき、明活にして思慮深く、そうそう道を履み外す事もありません。
「本物の指南者」や「腕の有る占い師」と言う者は「思い込み」を可能な限り排除します、「自分の主観に過ぎる」「未熟な判断力」「我を張る」「正しいという思い込み」・・・これらがあると「正しい運勢」「正しい人生」「正しい生き方」が観えて来ません。
故に、「素直さ」を深く、生涯に渡って養うのです。
又「素直」とは「純粋」と言う領域を大いに含みます、「純粋に運勢を観る」「純粋に判断する」「純粋に感じる」・・・これが出来なければ「占いの神髄」には到達できません。それは何故か・・・占いは「感じる」という領域のものだからです。
では、「素直」とは具体的にどういう精神なのかと言えば・・・
◆前提が無い=前提があると「思い込みが生じる」
◆自分を無にする=「強い我、主張」があったり「主観に因る過ぎる判断」があったり「未熟な価値
感」を以って判断しては正しく運勢を判断できない。
◆透明感を持つ=色眼鏡で物事を観ると、色に染まって観える、透明な眼で観るからこそ本来の色が観
える。
「占い」とは様々に言えますが、一つは「占いは感じる事」と言えます、其仙流の占法の「無相」は「雲や光りを観る」占法ですが、その光りや雲を「どう感じる」かも含みます。
「麻衣神相法」の「気色、神氣」も無相と同じ事が言え、「気色、神氣」を観ると同時に「如何に感じるか」も求められます。
この「光りや雲、気色、神氣」が「運勢そのもの」ですから、これを正しく判断出来ない様ではお話しにならないので、事前に「素直さの養いの重要性」を説いているのです。
では、「素直の効用」を説明しましょう。
①『私心にとらわれない』
「素直な心と言うものは
私利私欲、過ぎる主張
未熟な価値観などに
とらわれる事の無い心
故に本質を観る事が出来るのである」
一般の方達は物事への判断は「主観」に因る所が大変、大きいものですが、「未熟な人間性の主観」だとしたら、如何でしょう、当然「正しい判断、本質的な判断、道理を得ない判断」などに陥る事になります。
その様な日々を積み重ねて行くと、「自分の判断が一般的、自分の判断が正しい」と思い込んでしまいます、「物事の是非」を出す時に、気を付けなければいけない事は「一般的だから正しい、多数の賛成意見があるから正しい」とする所です。
もし世間一般が間違っていたら、不十分だったら、その答えは根底から覆る事になります、それが人の運勢を観て「人生を説く、生き方を説く、成長を説く」お仕事の「指南者」なら尚の事、慎重に指南を選ばなければいけません。
「占い」は「どこまでも透明感を尊びます」「どこまでも純粋を求めます」「どこまでも素直に感じる」のです、その為には「私心にとらわれている」様ではいけません、「我の強い者、過ぎる主張をする者、こだわりが強すぎる者、自分に素直さが不十分だと自覚が無い者」は先ずは「素直の養い」に重点を置かなければ、必ずいずれ行き詰り、生き詰まります、重々心得る様に。「私心は働くけれども、とらわれてはいけない」
②『耳を傾ける』
「素直な心と言うものは誰に対しても何事に対しても謙虚に耳を傾ける事である」
「聞く耳を持つ」はとても重要な事です、「聴く耳を持てない、持たない人」は「自分の狭い視野で物事を判断します」それが上手く行っている時は良いとしても、そんな事がいつまでも健全に続く事はあり得ません。
又「聞く」は「聴く」に重きがあります、「聞く」は単純に「音を聞いている、自然と耳に入って来る事」ですが、「聴く」は「注意深く意識してきく事」です。
そうする事で「言葉の中に含まれている真意や別の本心」に気付く事も出来ます。
しかし「耳を傾ける」時には一つの注意点があります、それは「謙虚に聴く」です。
「高を括って聞く、聞いてやっているという姿勢で聞く」などという傲慢で独善的な聞き方をしても、「観えない言葉聞こえない声」には気付く事が出来ません。
「占い」は「相談者の悩みを解決する事、又はその手掛かりを示す事」です、故に「耳を心から謙虚に傾ける事」が必須となるのです。「耳は心の耳、聞くは聴く」
③「寛容」
『真に素直な心に達したら
何を許し、何を許さずかが
理屈を超えて分かる様になる』
「寛容」とは「心が寛大で、よく人を受け入れる事、過失を咎めたてせず、人を許す事」を言います、まさに現代人に足りない要素と言えるでしょう。
何かあると「責任追及」「批判はするのに、自分の言動の責任は負わない」など「無責任」の一つの原因も「心が狭い」から起こる事です。
「寛容」になる事で「心に余裕」が生まれます、これは「余裕が生じるから寛容になる」と似て非なるものです。
「寛容になるから心に余裕が生まれる」は「自らが先に寛容になる事で能動的に心に余裕を見出します」が後者の「余裕が生じるから寛容になる」は「先に心に余裕が生まれる」という前提条件があって初めて「心に余裕が生まれる」ので、「受動的」と言えます。
一般の勤め人ならば、ある程度は「受動的」でも良いかもしれませんが、「志がある者、経営者や政治家、大きく成功したい」などを望むならば、当然「先に寛容さ」が求められます。
人を指導する立場の指南者は当然「寛容さ」と言うものを心得ておかなくてはいけません。
「許す許さないを感情で判断するべからず」
④「理屈を超える」
『理屈は前提なれど
理屈を越えなければいけない時に
理屈に拘る様な者は
大した事はない人間である』
殆どのこの世の物事には「理屈」=「物事の道筋」と言うものがあります、でもこの「理屈」にはもう一つの側面があります、それは「屁理屈、こじ付け、無理筋、建前」の意味合いも含まれる時があります。
其仙流は「道理」を重んじます、「道理」とは「物事の道筋」と言う「理屈」と一見同じ意味合いを持ちますが、「道理」とはあくまでも「限りなく、自然的で、本質的である」と言う意味で、一方「理屈」は「人が人為的、又は作為的に生み出した道筋」と言う意味を含みます、この違いが分かるでしょうか。
又、「理屈を超える学び」を時として人は真っ向からぶつかり取り組まなければいけない時があります、「理屈に拘る人」はこの「理屈を超える学び」をせずに理論武装したりするので本質的な話しが出来ない事が多く始末が悪い所があります。
当然、指南の現場に於いても「理屈を超える」事は時として求められます、その様な時に「理屈一辺倒」の指南しか出来ないようであるなら、その貢献度は高が知れています。
人生は理屈のみで成り立っているのではありません、「偶然性や不確実性」なども大いに加味されるのです。
「理屈はあるが、拘るものではない」
⑤「実相が観える」
『素直の心というものは
物事のありのままの姿
本当の姿、物事の根っ子
というものが観える心である』
物事の本当の姿を理解するしないは、判断に重要な要素となります、表層的な部分や建前の部分のみで全ての是非を決めるのは愚か者のやる事です。
この「実相」を掴む事を邪魔するものは「他者の作為的、又は人為に過ぎる思考」や「本人の思い込み、我、間違った前提」などです。
実相が分からないのに是非を出すと当然間違った判断をする事になりますので、場合により周囲に迷惑を掛ける事になります。
この実相を観る事は「運勢や人生を観る」事を生業とする、指南者には大変重要な要素となります、相談者の運勢や人生の実相を察する事が出来ないようなら、それは「森を観て木を観ず、川を観て水を観ず」と同じと言えるでしょう。
又、実相が観える様になると「成すべき事が何か」を知る大きな手掛かりにもなります、これはどの様な人にも重要な事です。「やりたい事が成すべき事とは違う」
⑥「道理を知る」
『物事には道理がある
道理を無視して
己がやりいた事、言いたい事をする人は
道理によってままならぬ人生を
歩む事となる』
「道理」とは「物事の道筋、物事の本質的で正しい在るべき姿」という意味です。
人の世は生きづらい側面があります、時に窮屈に感じたり、重苦しく感じたりします、それが自分の人生なら尚の事そう感じるのではないでしょうか。
でもそれは「道理を知らない」からという側面もある事を知って欲しいもので、「道理を知ったら」今まで、生きづらい、窮屈、重苦しいと感じていた事が軽やかに感じる事もあります。
「礼儀、敬愛、仁義、孝悌」などは一つの「道理」です、この「道理」を先ずは知る事が非常に大切で、次にこれらの道理を実践する事で深く理解し修得して行くのです。
「礼儀の通らない職場、敬愛の無い社会、仁義の無い友人関係、孝悌の思いが無い家族」この様な事がまかり通る社会は歪(いびつ)でしかありません、現に今の日本がこの様な有様になりつつあります。
道理を教える事も指南者の務めの大きな一つです。「石が流れて、木の葉が沈むは道理でない」
⑦「本質を悟る」
『素直には物事の本質を
悟る働きがあります
本質が無い物事とは
水の無い川、木々の無い山と同じで
中身が無い』
「本質」とは「それが無くなると存在し得なくなる要素」の事です、物事には「道理と共に本質」が存在します、例えば「内燃機関の自動車」で言えば「エンジン」が「車の本質」と言えます、又、パソコンで言えば「CPU」、パンで言えば「酵母菌」、人間で言えば「精神」がそれぞれの本質と言えるでしょう。
「本質」を無視した言動をいくら積み重ねても、左程の価値や意味はありません、場合によっては周囲に害をなしたりしますので注意が必要となります。
「本質」の分からない人の一つの性癖は「反対の為の反対をする」「流れを止める」「和を壊す」「良いものや、美しいもの、価値あるものをそう取れない」など多大に問題があります。
この「本質」を示す事も指南者の大事な務めの一つです、本質を教え、成長を促し、本物に育てる・・・これが指南者の本質的な在り方の一つです。
「本質」を失ったら、それは唯の「無筋、無法、無道」と言うものです。「実益を取るなら実を取れ、心の清しさを求めるなら花を取れ」
⑧「価値を知る」
『価値を知る者は
その価値に未来、人生、豊かさを
見出す事が出来る』
「素直の養い」を重ねて行くと次第に「人格の基礎」が仕上がって行きます、そうなると物事や人物、品物の「真の価値を知る」事が出来ます。
又、「価値」と言っても二通りあり、一つは「変化をする価値」もう一つは「不変的価値」の二種類です。
例えば「お金」は大変生きていく上で大切なものですが、「お金の価値は変化」をします、故に「不変的価値」では無いので、優先されるべきは「不変的価値」です、「不変的価値」とは「人の命」が上げられるでしょう、その「命」をどの様な価値あるものにするかは人それぞれですが、そもそも「命」が無ければ生きて行く事すら出来ない「絶対的価値」と言えます。
もっと、足元に目を向けたら・・・「親の躾け、先生の教育的言葉」なども一つの大きな「価値」と言えます、「人が迷惑する事はするな」「社会や周囲の為になる事をせよ」「弱い人を守れ」などなど、幼い頃、親や学校の先生から誰しもが言われたはずです。
これらの言葉の「意味と価値」を知る知らないはそのまま「人生の軽重」となります、軽い人生は軽い学びをしてきた証です。「価値あるものに出合う事がすでに恵まれている」
【まとめ】
「素直の効用」はこれだけに止まらず、他にも様々あるはずですが、先ずは此れ等が大事と言えるでしょう、「素直」を軽々に扱う者は「独善的な生き方、周囲に不快感や迷惑を掛ける生き方、傲慢な生き方」をしている人です。
「素直」を深く養う事は「己の人格を修める」という事の始めにいるのです、後は純粋に初心忘れる事無く積み重ねて行くのです。
「素直か素直じゃないか」これ一つで人生が想像以上に大きく変化します、特に其仙流の学びは玄妙で玄奥です、その場の「一喜一憂」で判断出来るものではありません。
疑問に思う事は素直な姿勢で質問をし、未熟な判断を振りかざさず、じっくりと腰を据えて学ぶ様に。
「素直の尊さ」は計り知れないもので、「人間関係に於いても、仕事に於いても、人生を生きるにも、運勢を観るにも」様々な事に対して「素直さの養い」が求められます。
素直とは「自分を一度横に置く事、自分を無にする事、前提を無くす事」です、多くの人が「素直」ではありません、心の底からの素直さがあればある程「達人、名人」に成って行きます。
第二義 「三徳、謙虚」 「謙虚ならざれば、いずれ虎の尾を踏む」
『謙虚な構えが有るか無いかは
摩擦を得るか、発展を得るか
謙虚があると禍そのものが遠ざかる』
「謙虚」とは「慎ましく、相手を尊重する事」と其仙流では定義しています、日本人は海外の人から見れば「謙虚」に観えるそうですが、そもそも海外には「謙虚」という概念自体が無い国もあります、「人生は主張をして生きて行くものだ!」とする文化の国もあります。
この「謙虚」は「美徳」にも通じるもので、深い謙虚の養いが指南者なれば求められます、しかし、「謙虚」と言ってもただの謙虚ではいけません、「頭を垂れて謙虚、腰を折って謙虚、心から謙虚」をして初めて本当に「謙虚」と言えるのです、現代日本人の多くがこの様な「謙虚さ」があるでしょうか?
又「謙虚」と言うものは「相手が誰であろうが」するもので、例え「程度が低い人であろうが、無礼者であろうが」一定の「謙虚さ」を以って対応する事が望まれます。
「謙虚」を養わず傲慢に生きていると、思わぬ落とし穴に陥る事もあります、それが小さい落とし穴だったらまだ良いでしょうが、「虎の尾を踏む、熊の頭に石を投げる」様な「大きな落とし穴」の場合は致命的です。
指南者は謙虚に相談者に向き合い、謙虚に運勢に向き合い、謙虚に指南をするのです。「謙虚な精神が深く養われているならば、驕り高ぶる事が出来ない」
第三義 「三徳、感謝」 「徳を積む人間は感謝を忘れない」
『善意に善意で応える
言葉だけの感謝ではなく
心から応えたい』
「感謝」とは「有り難く心から感ずる事」です、しかも「有り難い」とは字の通り「そうそう無いほどに嬉しい事」という意味です。
例え相手が小さな事と思っていても、自分からすると「深い善意」を感じ、「有り難い」と思ったら「感謝」の意を示すべきです。
折り目節目で「感謝」を示す事が出来ない様な人間は「傲慢で驕り高ぶって生きている人」でしょう、「有り難い」事をしてくれたから、無礼な言動は慎まなければいけない・・・・当然の事です。
日頃の感謝、格別な感謝、感謝にも様々あるでしょうが、人が「真心からの善意や良心」から出た言動には「感謝の意を示すべき」で、「感謝」を軽んじると、次第に周囲に人がいなくなり、いざ困っていても誰も助けてはくれません。
指南者は「相談者の悩みを解決する、若しくはその手掛かりを示す」事をその役割としていますが、相談者と共に指南業を通して「成長」もするのです、故にどの様な相談者にも感謝の念や意を持つ事が必須なのです。
「感謝」が出来ない人は恩知らずな人と言えるでしょう。「感謝の輪が広がる、それが本当の和」
【三徳まとめ】
指南者は「徳」を目指さなければいけません、「徳」とは「自分の出来る最善を他者に尽くす事」を言います、「徳が身を助けてくれる」事もあります、「徳があると人が集まります」「徳があると道が開けやすくなります」「徳があると運に恵まれやすくなります」
でも、徳を積むのに何か特別なボランティアや奉仕活動をするのは根本的に違います、「徳を積む」とは「足元の、日常の中の」当たり前にある事です、その最たる例は「仕事、生業」です。
我々、指南者は「仕事」を通して「徳を積む」のです、一人でも悩みの人生を前に進めてあげ、一歩を踏み出す言葉を絞り出し、幸せを自ら勝ち取り生み出す事が出来る人間に成長させ、その恩恵を周囲にも与える事が出来る人を育てる・・・指南者の理想的な姿の一つです。
それ程の指南者になるには「学ぶ姿勢が重要」です、自己流の学び方では決して大成は出来ません、其仙流が尊ぶ「三徳」に「本物の指南者に成る為の要素」が「凝縮」されています。
この先に何か躓き、伸び悩む事があれば、「三徳」を思い出しなさい、心の助けになるはずです。
中でも「三徳」の肝要な所は「素直」です、「学びは素直に始まり、素直に終わる」と其仙流の先人達からの口伝です。
「三徳」を深く学び「学ぶ姿勢」を学びましょう。
第四義 正しく学ぶ姿勢 五大則
「本物」に成る為には、皆さんが思っている様な事では恐らくまだ「本物の領域」には達さないでしょう、多くの人が「本物の占い師」に成るには「本物の占法」さえ学べば良いじゃないか!と思っているでしょうが、それは大きな思い違いです。
其仙流が定義する「本物の条件」は以下の様なものです。
①「物事の本質が分かる人格形成を成されているか」
②「本物の占法を深く学び、習得しているか」
この二点が高い水準で求められます、又「人格形成」に重きがあり、「物事の本質が分かる人格形成」を成されていない以上、如何に「本物の占法」を習得してもいずれは、伸び悩み限界が来たり、自己流に捻じ曲げたり、場合により傲慢で自己満足な迷惑を掛ける様な占い師になる可能性があります。
そこで其仙流は以下の五つを初めに学びます。
①「どこまでも自分作りが重要」=人格形成をする事で物事の本質を知る事が出来る。
②「他占法の過誤」=他占法の間違い、誤りを知る事で如何に他の占法が実践に通用しないかを悟る。③「どこまでも本気が問われる」=占いは遊びでは無いのです、真剣に生きる人の為のものです。
④「仕事の意義」=この占いの本来の意義を知る事で、自らの仕事にブレが生じない、脇道に逸れな
い。
⑤「占い師は同時に経営者である」=経営を学ばないと生業を維持できません、経営を深く知り己の血
肉にする。
これら五つをして「五大則」と呼び、これらを先ず初めに学び、「正しく運勢学を学ぶ姿勢を学びましょう」
①「どこまでも自分作りが重要」
「自分作り」―多くの人がその気はあっても、真剣に取り組む事があまりないものでしょう。
でも指南業には「自分作りは必須」なのです、昔の指南者や占い師は例え、占法の原理が間違っている様なものを使用しても人格を養い磨いていたので、心に響く事を指南出来ました、ですから何とか指南業でやっていけたわけです。
しかも自分作り、所謂「人格形成」は高い水準を指南者は求められます、「人生を説き、生き方を説き、成長や学びを指導し、如何にすれば良いか」を指南するのですから、当然、卓越した人格を有していなければいけません。
目指すべき人格形成は「人格者」の領域です、「物事の本質を悟り、すべき事やるべき事を悟り、その上で徳を積む者」が其仙流で言う所の「人格者」です。
いくら本物の占法を学んでも、それを扱う本人の人格が程度の低い者ならば、いずれ限界が訪れ、人に害を成す存在に成り兼ねません。
又、「偽物、紛い物の占法」を使用して指南をした所で、偽物で出た答えが正しい事は殆どないので、「徳を本質的に積んでいるか」と問われれば当然、「否」となり、場合によっては「自己満足な占い師、相談者に迷惑を掛けている占い師」になるのです。
正しい占法は当然としても、大前提にそれよりも優先される事は「人格形成」に在りです。
この「人格形成」に終わりはなく、終生に掛けて養う事が肝要です、人格形成を軽んじる者は自らの人生を以ってその代償を払う事になります。
「自分作り」とは「物事の本質を悟る」為に養う事も重要な事ですが、人としての「礼儀、仁義、配慮、温度、距離感」を発揮する為にも非常に重要です。
これ等の学びを如何にするかと言うと、当流は「東洋哲学」の学びを一つの軸に置いています、「老子の道徳経、荘子の荘子、孔子の論語」を其仙流は「三大貴書」として、先ずはこれらの学びから修行が始まります。
老子や荘子は少し難解な所があるので、先ずは「孔子の論語」を中心に様々学びます。
「哲学」とは「哲」の文字にも含まれる通り「道理に明るい」と言う意味です、物事の道理を知る事によって、本質を悟る学びをする学問が「哲学」なのです。
故に指南者には必須の学びであると言えます、くれぐれも軽々に哲学を学ぶ事が無い様に。
②「他占法の過誤」
この業界にありがちなのは占い師になろうとする者が「占法」を選ぶ時に多くの人が「好み」で選んでいるという事です、相談者も同じで「タロットで占って欲しいんですが・・・」とか「スピリチュアルで見て欲しいです」などと言います。
これはそれぞれの占法が「本物である」と言う前提に立っているわけですが、もし偽物ならどうでしょうか・・・当然「間違ったアドバイス、見当違いな答え」になるでしょう。
多くの一般人や同業の占い師は、自分の好きな占法や信じている占法が「本物であって欲しい、本物に違いない、本物でなければならない」と思っています。
では「本物の占法」とは何か・・・それは「正しい原理が働いているか」の一点です!
目に見えない運勢と言う存在を観るには「観る為の原理、原則」が必ず存在するはずです、例えば「タロットカードが何故、運勢を観る事が出来るのか」「姓名判断で何故人の運勢を観る事が出来るのか」「何故、九星気学で人の運が観えるのか」という事です。
車で言えば「エンジン」が「原理、原則」に当たります、「エンジン」が無ければ車は走りません、これと同じで占法にもエンジンが必ずあるのです。
つまり、多くの占法が「原理、原則が存在しない、間違っている」状態です、又、一方でよく言われるのが「霊感、スピリチュアル、霊視」などは能力や精神力を使用するので「原理、原則はありません」などと言う主張をされる方がいますが、これも全くの誤りです。
其仙流の「無相」は「一種の透視術」で、確かに人の能力の一つですが、それでも「原理、原則は存在します」多くの人が間違っている事は「精神力を使用する占法は思いや思念を使う力だから、そこには法則性は無く、思いや精神の純粋さや念じる度合い」が源であるとする所に大きな誤りが存在するのです。
そんな、アバウトな事で見えない運勢を観る事は出来ません、其仙流は「無相」にしても「麻衣神相法」にしても、その他の占法にしても全てに於いて「陰陽論」を「原理、原則」その源にしています。
恐らくは「陰陽論」以外で未来を察する方法は存在しないのではないでしょうか?
人の心や気持ちにも一定の法則性が存在します、「精神の何をどう使用するのか」ここを具体的にその論拠を述べないと唯の思い込みでしか無いのです。
信じたい占法、やりたい占法」を以って運勢を謀る事は相談者を迷わす大きな原因となります。
又、「占い」とは「運勢を観る事」が大前提となります、ここを多くの占い師が思い違いをしていたり、そんなに重要視していない状態です。
例えば、カード占いは運勢を見ているのではなく「カードを見ている」のです、それに対してカード占い師は「カードを通して運勢を観ているのです」と反論をします、そもそもここが間違っているのです。
では、「カードを通して運勢を観ている」ならば、何故「カードを通して運勢を観る事が出来るのか」という「原理、原則、法則性」を示さなければいけません、そこに大きな欠けがある以上、カード占い全般は偽物の占法である言えるのです。
又、「運勢は観る事が前提である」と先にも言いましたが、多くの占法は「数字で計ったり、星座や星で計ったり、青年月日で計ったり」と色々な理屈で運勢を語りますが、一歩踏み込んで言うならば「運勢と言うものは直接的に観る事」をしなければ到底その是非は分からないのです。
例えて言うならば、「人の命を観る」事が出来るか?という事です、人に命を直接的に観る方法が無いから、医学は他の様々な方法で「健康を計る」のです、つまり現代医学ですら命そのものを観る術を持たないのです。
それは何故か・・・それは命が無形だからです、故に命を入れる入れ物=肉体を看る事で何とか命を観る代替としているのです。
ですが、「人の運勢」となると「代替する方法が存在しません」、どうしてか?・・・それは、運勢は現象に先んじて生じるからです、何かが起こる前にはその前兆が運勢に現れます、それを察する事が占いには不可欠だから、代替法では間に合わないのです。
運勢は流動的で変化に富みます、時に激しく躍動し、時に不動の如く観えても観えない所で動いています、その様な運勢を微に入り細に至るかの如くに観て判断をしなければいけないのです、それには「直接的に運勢を観る術(すべ)を持っていないといけない」のです。
そもそも、「運勢を観る原理、原則」はそんなに多く存在するわけが無いのです、空を飛ぶ方法は「揚力」を利用する事に一貫されるのと同じです。
今現在存在する99,9%の占法は原理、原則が存在しない、又は間違っているもので、その原理、原則も人為的に創造されたものを源とする全くの「偽物、紛い物」なのです、その様な占法を用いて人を救ったり、導いたりする事は不可能なのです。
③「どこまでも本気が問われる」
この「指南業や占い業」は皆さんが思っている以上に「本気度」つまり「真剣度」が問われる務めです、ここがフラフラする様な者は顔を見れば一発で分かります。
「憧れだけ、お金儲けのみ、名誉や地位の為」この様な者は一時は指南業で生活が出来るかも知れませんが、年老いて、いつまでも占いで生活が出来るかと言えば、殆どの者が脱落します。
又、仮に晩年までも指南業で生活をしていても、間々ならない生活になるでしょうし、いずれは如何様にもボロが出たりします。
「本気」と言っても其仙流が言う本気は「真剣」です、「真剣」とは「命懸けの姿勢」という事です、「何をそんな大げさな」と聞こえて来そうですが、それは「命懸けの意味が分かっていない者」若しくは「命懸けの仕事に巡り会っていないか」のどちらかでしょう。
「本物や腕の有る指南者」には「命懸けの仕事が入って来る」事があります、又、相談者が「命懸けの相談をする事もあります」その様な時に、こちらも「真剣に対応せねば、観えるものも観えなくなります」つまり「命懸けの如くに真剣に取り組まなければ本物では無いし、実践では通用しない」のです。
又、「真剣の覚悟」も一度や二度の覚悟では駄目で、困難な相談、厳しい現場の度に覚悟のし直しをする事により、「本物の覚悟」が仕上がって来るのです。
又、この「本気、真剣」というものは「修行時代、学びの時代」から心得ておかなければいけません、実践になったら覚悟を決めます・・・では遅いのです。
「覚悟をして、挫折し又覚悟をする」・・・この繰り返しをするのです。
其仙流の占い教室を真剣に学び深め、実践で真剣に臨み、挫折、失敗、不十分さを痛感する・・・こうでなければ本物に成るわけはないのです。
現代占い師の多いのは「下積み」を積まない事にあります、下積み時代は当然儲けも少なく苦労もします、指南業の始めは指南が中々上手く相談者に伝わりません、時には解釈の間違いもします、時には相談者に飲まれる事もあります。
その都度、自分の腕の未熟さを思い知り、真剣度の見直しと覚悟の決め直しをするのです。
この「本気、真剣」と言う構えには「真面目、勤勉さ、真心」と言う要素も加味する事を意識しなければいけません、時に「本気、真剣」と言うものは自分本位にもなる事に注目すべきで、その様な「空回り、独善的」な「本気」では又いけないのです。
幾分か走ったら、ふと立ち止まり「本気、真剣」の見直しをして微調整する事が重要です。
「本気で仕事に取り組めない人」は、その人生も真剣に生きていない人です、その様な者は指南業、占い業をする資格はありません。
④「仕事の意義」
「仕事の意義」つまり「占いの意義」ですが、実はこれは非常に深刻なテーマでもあります。
「占い業、指南業の意義」とは要するに「社会的に占いの必要性がどこにあるか?」という事に他なりません、現状の巷にいる様な「占い、占い師」に「社会的意義」を見出す事が出来るのでしょか、当流はそうは思いません。
ここは大変、重要な事なので、「適当に片づけたり、見て見ぬふり、思い込み」などで終わらせるわけには行きません。
古代中国に於いて占いは「王族」が生み出し、そして継ぐものであり、次第に「政治や戦」に活用され、そして「生活そのもの」に深く活用される様になりました、それにつれて「占い」も徐々に一般人にも広がる事になるのですが、同時に「紛い物、偽物の占い」も生まれ、広がる事になります。
其仙流は「指南業の意義」の前提に「社会や人に本質的に役立ってこその占いである」としています、その上で「人に対しては、生き方を説き、人生を説き、学びと成長を説く」のです、又「社会に対しては、個人的に社会貢献を目指す、仕事で社会貢献をする」のです。
この積み重ねが「徳を積む事に」に通ずるのです。
「占いは遊びでは無い」とは其仙流の先人達からの口伝です、「社会的意義の無いものはどんなに稼ぐ事が出来ようとも、それは仕事では無い」のです、「お遊び」なのです。
現代占いの多くが「戦争地帯、紛争地帯、貧しい地域」などで通用するでしょうか?
現代占いの99%は「占いごっこ」をしているに過ぎません、「占いごっこ」をして「自己満足に浸り、自分こそ本物だと」思い違いをしているのです。
「本物の仕事」とは「社会に通用し、広く人々にも通用するもの」であり、それが「仕事の意義」がある証でもあるのです。
今の占いは社会的意義はあるはずもなく、「お遊びの占い」に成り下がっている状況です、この平和ボケした日本だからこそ通用するだけの事で、100年後も300年後も千年後も今の占いが存在していると思いますか?
現代に於いても「人格を磨き養う者」からしたら「現代占い」は全く「価値無し、意義無し、意味無し」と一発で看破されます。
「お遊びの占い師になる」という事は引いては「占い業界そのもの」を将来的に破滅に導く行為だと自覚しなければいけません。
このままでは、そう遠くない将来に占いは滅ぶでしょう、その兆候はすでに現れており、其仙流は「占いは、緩やかな滅びの段階に入っている」と観ており、これにブレーキを掛ける為に、業界の「大掃除、大洗濯」をする為にも活動して行きます。
どんな仕事だって「遊び」ではどこまで行っても「遊び」の範疇を超える事が出来ません、「本物、本当の仕事、生業」とは「真剣な構え、本物である、本質的な貢献、そして生産的である」だからこそ「価値があり、意義がある」のです。
どこでも通用する、真剣に生きる人から求められる様な本物の占い師を目指しましょう。
⑤「占い師は経営者」
占い師は基本一人一人が独立しています、其仙流は流派ではありますが、お客さんは其仙流の看板に付くのではなく、一人一人の無相使いに付くのです、その様な意味で言うならば「占い師は一人一人が経営者である」と言えます。
「占い師は経営者でもある」・・・これをしっかりと練っておかなければ必ず、困った事になったり、いつまでも稼げない指南者になります。
「多くの顧客を抱えていれば良いんじゃないの?」と思うかもしれませんが、それは根本的に間違っています「顧客を抱え、金を稼ぐ」という事は「時間稼ぎ」は出来ますが、「経営」とは違います。
例えば、「コロナウイルス問題」で言えば、「顧客を抱えている」という事は確かに良い事ではありますが、コロナ問題が長期化するにつれ、「来客の減少、相談の減少」=「売り上げの減少」になります。
この様に説明すれば「お金を持っている」=「時間稼ぎ」と言う意味が分かると思います、では経営とは何か、それは「物事、事業を維持、達成する為に行う判断」を言います。
コロナ問題で言えば「コロナ対策として、店内の空間殺菌対応、それに伴う機器の購入、消毒液、マスクの備蓄、他の感染対策を考える」これらに始まり、「減少した相談者に対しての対策=事業の継続方法」や「宣伝、鑑定方法の新たな模索」など多岐に渡り、しかも短時間、短期間でこれらを判断しなければいけません。
経営とは「日常だけ」でなく「もしもの時」の事も考える事が望ましく、日頃から色々な社会的情報を耳に入れておく事は重要となります。
又、経営者は本来「人格的に優れた者」でなければ出来ない側面がありました、だからこそ昔は「帝王学、哲学」などを経営者は学んでいました。
経営者も人間です、故に本人の人間性や人格性と言うものが経営にも反映されます、故に個人の人格の養いも必須となるのです。
そして、経営も生き物です、一瞬一瞬変化し、それに対応する対策、構えを求められます、ボケっとしていたらあっという間に変化に対応できなくなり、一歩も二歩も遅れる事になり、追い付くのにかなりの苦労を要する事になります。
又、経営を意識し、立派な経営者を目指す事は「経営者の相談」が来た時に役にも立ちます、「雇われ、勤め人、サラリーマン」と「本物の経営者」は思考方法や生き方、ものの観方が根本的に違います、経営者が相談に来て、雇われの感覚しか分からない者が経営者の相談に対応出来るでしょうか?
又、どの時代も同じ事が言えるのは社会が好景気で上向いている時は誰でも成功するものですが、「バブル崩壊、不動産バブル崩壊、ITバブル崩壊、リーマンショック」などの様に「厳しい時代」になると「本物しか生き残れない」のです。
つまり「偽物、紛い物、二級品、二流三流」は時代によって淘汰されるのです。
「経営者に求められる条件、必須な心構え」は「情報や世間に敏感になる事」「深い人格形成を養う事」「物事の本質を悟り、見識を以って判断をする事」「仕事に真剣に取り組む事」「やるべき事をやり、すべき事をする」これらが最低条件となります。
経営者は並みの者では成れません、人一倍苦労を惜しまず、努力を課し、失敗を重ね本物の経営者に成って行くのです。
経営は「発想とアイディア」で構わないと考える人がいますが、それは間違っています、経営はその人の人格に裏打ちされたものなのです。、その人の人格が必ず滲み出て反映されるものなのです。
コロナ問題に後れを取る様な経営者はその生き方もどこか油断や隙がある人と言えるでしょう。
【まとめ】
「素直、謙虚、感謝」の其仙流が言う所の「三徳」と、①「自分作りに本気なる」②「他占法の過誤を学び如何に多くの占いが間違っているかを知る」③「どこまでも本気は問われる」④「仕事の意義」⑤「経営者である」の五大則をしっかりと学び腹に修め、又これからも心掛けて行く事で「正しい学び方、正しい取り組み方」の基礎が出来て来ます。
お医者さんも、弁護士も、設計士も、皆さん「専門職」というものは「自己流」では成りません、自己流は必ずどこかに歪みが生じ、成功、大成しません。
「占い業、指南業」も同じ事が言え、特に「人格の形成に重きが在ります」、指南者の伸び代は「人格形成に始まり、人格形成に終わる」と昔から言われます。
本物の技術だけを学び盗んでも必ず限界が来て行き詰まります、時として生き詰まる事もあり得ます、其仙流の精神を深く素直に謙虚に学び、伸び悩んだら基本に立ち返り見直し、又一歩を積み重ねて行くのです。
「本物」は始めから「本物」ではありません、「事情練磨」を自らに課し徐々に「本物」に成って行くのです、「偽物、本物の違いが分からない」昨今に本物たらしめる姿勢を世に見せつける様に本物の占い師を目指す事を願って止みません、皆が腕利きの、例え小さくともキラリと光る本物の無相使いに成る様に願っています。
